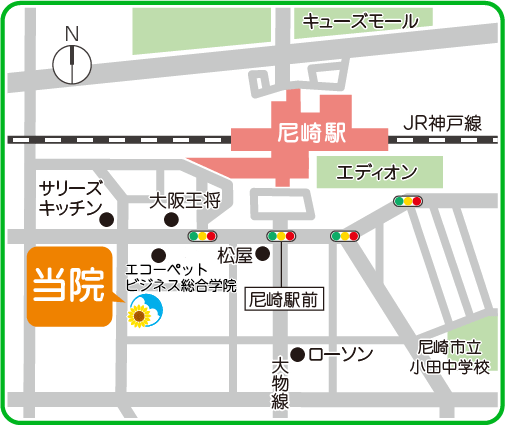療育整体は、松島眞一先生が開発された整体法で、元々は発達障害のお子さんの発達を身体に働きかけて促していく技法として生まれました。
先生が療育整体に取り組まれたきっかけは、娘さんが発達障害と診断され、お薬を勧められたことだったようです。主治医より「脳の障害」と伝えられるも脳のどこが悪いのか、どこが悪いのかもわからないのになぜ薬を勧められるのか、など疑問が次々に膨らんだようです。
整体院をしておられた先生は、発達するのは身体であり、身体から発達の問題をみていこうと考えて、娘さんの動きや姿勢などをよく観察しました。すると、娘さんは歩き方が変でよく転倒していたそうです。
中医学には皮脳同根(皮膚と脳は同じルーツ)という考え方があります。これは発生学的にみても妥当なことで、受精卵が細胞分裂していく過程で外胚葉、中胚葉、内胚葉に分かれていきますが、人間の皮膚と脳は、同じ外胚葉から派生したものなのです。
皮膚は多くの感覚(触覚だけではなく)を感知して、大量の情報を処理している器官であり、脳に直結しています。つまり、皮膚を刺激することは、脳に刺激を与え、全身の神経発達を促すことなのです。
娘さんへの施術により、娘さんの歩き方が変わり、バランスが悪くよくこけていたのがこけなくなったり、授業中に手を上げなかったのが手を上げるようになったり、昼休みに遊ばなかったのが友だちと遊ぶようになったりなど、次々とうれしい変化が生まれたのです。
親として娘さんの身体をよくしてあげたい、不便さを少しでも解消してあげたいという親心から始まった整体は、後に療育整体と名付けられ、今では全国各地で講習会が開かれ、プロの療育整体師も生まれています。
療育整体は、「筋肉、関節の動き、体軸をコントロールすることで、人間の理想的な形(解剖学的肢位)を作り、血流を上げて、発達、成長に必要な身体機能を向上させる全身調整法」と定義されますが、一言でいうと「血の流れをよくして姿勢をよくする整体」と松島先生は説明しています。
なぜ、血の流れをよくすること、姿勢をよくすることが大事なのでしょうか?療育整体の理論的な基礎には、身体心理学や中医学があります。身体心理学では、姿勢や動作が変わればメンタルが変わるという考え方をします。つまり、気持ちが沈むからうつむき加減になる、肩を落として歩くようになる、のではなく、うつむいたり肩を落として歩くから気持ちが沈むと考えるのです。
療育整体では、発達障害を「神経発達の不具合」がある状態であり、「部分的な未発達、部分的な未成熟」がある状態と考えます。姿勢をよくすること(「骨軸で立つ」こと)により、身体が整い、血流が整い、こころが整い、未発達な神経は発達、成長していきます。この「骨軸で立つ」身体にしていくことが、療育整体の一番の目標になります。
骨軸で立つとはどういうことでしょうか?それは、重力がきちんと骨格に乗っている状態のことをいいます。重力の負担が筋肉にかからない姿勢こそが、関節や筋肉の連動性が一番上がり、動作が滑らかになり、余計な緊張が取れるのです。
身体に負担がかかる姿勢では、筋肉は疲労し、筋肉の疲労は筋の収縮・弛緩異常を生み、身体のゆがみをもたらします。身体がゆがむことで滞りが発生し、血の巡りも悪くなり、冷えや痛みなどを生じ、身体が固くなり、さらにゆがみが固定されるという悪循環を繰り返します。
ですので、まず姿勢と血行をよくすることが大事になります。神経と血管は伴走しており、血流を上げると神経発達がもたらされます。京都大学の研究で、ニワトリの各細胞が神経系と血管を作るときに、双方の細胞が相互に情報伝達をしながら神経系と血管を作っていくことがわかりました。神経、血管のワイヤリング(相互依存関係)に不具合が生じると、神経発達にも支障が生じるのです。
血流をよくすることは重要ですが、そもそも血が作れているかが大事です。血を作るには食事に注意することが大切になります。このように療育整体では、施術により身体を整えること以外にも、食事の見直し、子どもとのコミュニケーション、家族や夫婦関係なども重視しています。
話をまとめます。
療育整体の目的は、血の流れをよくして、その人に合った理想的な姿勢を自然に取れる身体を育てることです。
療育整体は身体心理学や中医学をベースにしており、①血流を上げる②皮脳同根③骨軸で立つ、といった考え方をします。
姿勢が悪いと血流も悪くなり、集中力や体力・運動能力が低下し、自律神経が乱れます。姿勢が整うと身体が楽になり、動きやすい身体になり、自律神経も整います。そうすると、自発的な動きが出てきて社会活動もしやすくなります。
発達障害は生まれつきの特性だから治らない、ではなく、生まれつきの特性だとしても発達、成長していくことができる、治ることがある、と考えることができます。
療育整体の手技は数多くありますが、基本の手技は3つになります。
①入力
関節に微弱な刺激を入れることで、首や肩、背中の緊張を取り、重心を整えます(体軸が足裏の真ん中にくるように調整する)。
②縦横
人間には縦に動かすと整う方、横に動かすと整う方があり、縦にさすると身体が喜ぶ方を縦にさすり、横にさすると身体が喜ぶ方を横にさする手法です。日々の生活、活動のなかで、腕や脚の長さには左右差が生じますが、それが固定化されると重心が偏り、血流も悪くなります。腕や脚の長さを揃えることにより、血流を上げ、神経発達を促します。
③ゆらぎ
足首を持ち、全身に届くように揺らす手法です。背骨を揺らして背骨を柔らかくして血流を上げます。入力や縦横に比べて、より全身に働きかける手法になります。
実際のやり方は、書籍や動画などで見ていただければわかるように、こんなに単純でいいの?と思うくらい簡単です(押さえるべきポイントはありますが)。
療育整体は、
①特別な知識、技術がなくても、学んだその日から行うことができる(手技はとてもシンプル)
②誰に対しても行うことができる(その人の特性、状態を問わず、何かできることがある)
③場所や時間、体勢を問わずに行うことができる(いつでもどこでもどんな状況、姿勢でもすきま時間でも可能)
といった特徴を持ち、家庭で気軽に取り組むことができる大変間口が広いアプローチです(奥は深いですが)。
親と子のコミュニケーションの促進や改善、愛着の形成や修復にも役立つことかと思います。
ポイントは、できることをできる分だけ根気強く続けることです。
療育整体は、発達特性をもつお子さんの家庭だけでなく、お子さんの健康な成長を願うすべての家庭に取り入れてもらいたい手法です。
書籍:
療育整体 松島眞一 花風社 2023年
療育整体で「こころ」を育む 松島眞一 花風社 2024年
HP: